
|
| ���@�{�݂̊O�� |
�}����������A�ݑ��Â܂ň�т����T�[�r�X���
�@�����s������ɂ���Љ��Ö@�l�Вc��������a�@�́A�u�n��Ƌ��ɐ����鎜���݂̃g�[�^���w���X�P�A�v�Ƃ������O�̂��ƁA�}����������A�ݑ��ÁA���N���i�܂ň�т����T�[�r�X�Ɏ��g��ł���B�@�l�̉��v�Ƃ��ẮA���a49�N�ɓ��@�̑O�g�ƂȂ鑫���N���j�b�N���J�݂������Ƃɂ͂��܂�B���a54�N�ɓ����a�@�ɉ��g����ƂƂ��ɁA���a56�N�Ɉ�Ö@�l�Вc�������ݗ��B���̌�A�~�}�E�}������Â̒��j�a�@�Ƃ��Ēn���ÂN�ɂ킽��x���A���ʈ�Ö@�l���o�āA����24�N�ɎЉ��Ö@�l�����Ă���B
�@���݂̕a������150���ŁA���̓���͈�ʕa��78���A�n���P�A�a��30���A�����n�r���e�[�V�����a��42���ƂȂ��Ă���B�~�}��Âł́A�~�}��Ë@�ցA�n��~�}��ÃZ���^�[�Ƃ���24����365���̐��̋~�}�f�Â��s���A�N�Ԗ�3,000���̋~�}����������Ă���B
�@��Ë@�\�Ƃ��ẮA�S�����ǃZ���^�[�A�t�Z���^�[�A�������Z���^�[�A���f�Z���^�[�̋@�\��L���A���Âł͓��������Â⋾������p�A����̉Ȋw�Ö@�ȂǍŐV�̎��Â�������A��N�P���Âł��錌�Ǔ����Âɂ����́B���݂͊����������▖�����ǎ����A�s�����A�]���Ǐ�Q�ɑ��鎡�Â����{���Ă���B
�@����ɁA�ŐV�̈�Ë@��i320��CT�A3�s�EMRI�j�����A�v���Ȑf�f�ƂƂ��Ɏ��̍�����ÒɂȂ��Ă���B���̈���ŁA�n��̍���i�s���������A���n�r���ɂ��͂����A�}�����A���A�������ɂ����ăV�[�����X�ȃ��n�r������Ă���B
|
|
|
| ���@�����a�@�̑�����t�Ɖ����n�r���e�[�V�����a���̕a�� | |
|
|
|
| ���@�ŐV�̃��n�r���@�����葵�������n�r���� | ���@��Ë@��ł́A�ō����\��320��G���A�f�B�e�N�^CT�Ȃǂ� |
�@�l���O��̌�������ÁE���̕����{�݂��J��
�@�@�l�{�݂Ƃ��ẮA�����a�@�̂ق��ɁA�f�Ï�����V�l�ی��{�݁A�O���[�v�z�[���A�K��Ō�A�K��n�r���A�n���x���Z���^�[�Ȃǂ��^�c���Ă���A�ߘa5�N9���ɂ͈�ÁE���̕����{�݂Ƃ��āu�������f�B�J���v���U�v���J�݂����B
�@�����a�@�̌������̕~�n�Ɍ��z���ꂽ�u�������f�B�J���v���U�v�́A���@�ɕ��݂��Ă������f�Z���^�[�A�t�Z���^�[���ڐ݂��ċ@�\������}��ƂƂ��ɁA�n��ɕs������ɘa�P�A�Z���^�[�i�ɘa�P�A�a��20���j��V�݁B����ɁA�ݑ��Â�n�r���@�\���������邽�߁A�ݑ�f�Ï����͂��߁A�ʏ��T�[�r�X�̃f�C�P�A��f�C�T�[�r�X�A���Z�T�[�r�X�̗L���V�l�z�[���݂��Ă���B���x��Â���ݑ��ÁA���N���i�A�ɘa�P�A�܂ł��V�[�����X�ɒ��邱�Ƃɂ��A�@�l���O�Ɍf����g�[�^���w���X�P�A�̎�����ڎw���Ă���B
 |
|
| ���@�ߘa5�N9���ɊJ�݂����������f�B�J���v���U�B��ÁE���̕����{�݂Ƃ��Ċɘa�P�A�Z���^�[�A�t�Z���^�[�A���f�Z���^�[�̋@�\��L����ق��A�ݑ�f�Ï���f�C�P�A�A�f�C�T�[�r�X�A�L���V�l�z�[�����݂��� | |
|
|
|
| ���@����뉀�ł́A�����炵�̂悢���̂Ȃ��Ŋ��҂����n�r���Ɏ��g�ނ��Ƃ��ł��� | ���@�L�X������Ԃ̃f�C�P�A�̃X�y�[�X |
|
|
|
| ���@�ɘa�P�A�a���̕a���ƃf�C���[���B���₩�ɉ߂�����×{������Ă��� | |
�������̏A�C�ɔ����A�o�c���v�ɒ���
�@���@�́A����16�N������Ԏ��o�c�������Ȃ��A����19�N�Ɍ��������̈ɓ���j�����������ɏA�C���A�o�c���v��Ζ������P�Ɏ��g�݁A�E���̗̍p�◣�E���̉��P�Ȃǂ̐��ʂ��グ�Ă���B
�@�o�c���v��Ζ������P�Ɏ��g�o�܂ɂ��āA�ɓ��������͎��̂悤�ɐ�������B
�@�u�����������ɒ��C�����͈̂�Õ����ꂽ���ŁA���@�Ɍ��炸�S���̈�Ë@�ւ̌o�c���������A��Ï]���҂̗��E���������ɂ���܂����B�A�C��́A���݂̖@�l���O���f���A�n���Â���邽�߂ɋ}�����a�@�Ƃ��Ă̋@�\���������A��ÁE������т��ăV�[�����X�ɒ�����j��ł��o���܂������A���̕��j�����H���邽�߂ɂ́A�o�c�̗��Ē����Ɛl���̑������s���ł���A�E�������������������ċΖ�����������J�����̐������K�v���ƍl���܂����B�܂��A�����̓g�b�v�_�E���̎w�����߂������A�{�g���A�b�v�ňӌ����o�₷���E��������邽�߂Ƀ��[�_�[�̈琬�Ɏ��g�݂܂����v�B
�@�g�D�̉ۑ��c�����邽�߁A����19�N�Ɏ��{�����E�������x�����ł́A�قڂ��ׂĂ̍��ڂőS�����ς�傫������鐅���ł��邱�Ƃ��킩��A�Ƃ��Ɂu��L�v�A�u�����E�]�����@�v�A�u�Ζ����v��3�_�ŕs�������������Ƃ����B
�@�u�����A���@�ł͘J���Ǘ��ɕK�v�Ȃ��̂��قƂ�ǐ�������Ă��炸�A�E���̋��^�i���������Ă���A�����d�������Ă��Ă��s������������܂����B�J�����̉��P�ɂ������ẮA�Љ�ی��J���m�A���F��v�m�A�ٌ�m�̃A�h�o�C�X���A�A�ƋK���̉����l�����x�̍��V�i�������x�E�]�����x�̓����A���^���x�̉���j�A���l�ȓ��������ł���Ζ����x�����A�E�����������������Ă�J���������܂����v�i�ɓ��������j�B
��������������J������
�@�������x�ł́A�E���Ɋ��҂���E�����s�\�͊���ʂɖ��m�����A�E����l�ЂƂ�̓����̌���⏸�i�^�p���߂�7�i�K�̐E�\�������x���B����ɁA�E��ʁE�����ʂɐl���l�ە\���쐬���A���ȕ]���A��i�]���i1���A2���j���o�āA�l�ێ҂ɂ�锻���c�����{���A�����������F�����ŏI�]���Ɋ�Â��A�����A���i�A�ܗ^�ɔ��f����]�����x���������B���^���x�ł́A�E�\������̂ɔN��A�Α�������{���Ƃ��āA�����ʁE�E��ʂ̋��^�\���쐬���A����������s���Ă���B
�@�Ζ��̌n�Ƃ��ẮA����22�N����Z���Ԑ��E�����x�A��ΐ������E�����x�A����25�N����͖�ΐ�]���E�����x���B���݂̓t���b�N�X���x�⎞�ԒP�ʔN���L���x�ɐ��x�����A���[�N�E���C�t�E�o�����X�𐄐i���Ă���B
�@�܂��A�ݒu����@���ۈ珊�ɂ��ẮA��Ζ��҂֑Ή����邽�߁A24����365���̉^�p�Ɋg�[���邱�Ƃɂ��A�q��Ă��Ȃ��瓭����������E������������B
 |
| ���@�����₷���E����Â���Ƃ���24����365���Ή��̉@���ۈ玺��ݒu |
�����Ǘ��V�X�e���ɂ��E���̌o�c�ӎ�������
�@����ɁA�e�퐧�x�����Ă��A�E���Ɍo�c�ɑ��铖���҈ӎ����Ȃ���ΐ��x���蒅���Ȃ����Ƃ���A����23�N����u���Z�����a�@�����Ǘ���@�v����암��œ������A���N�����Õ���ł̓������J�n�����B
�@�u���Z�����a�@�����Ǘ���@�v�́A���Z���́u�A���[�o�o�c�v�̃m�E�n�E���x�[�X�ɁA�a�@�����ɊJ�����ꂽ�V�X�e���ł���A�a�@�����e�a���A���ː��ȁA���n�r���e�[�V�����ȁA��܉ȁA�㎖�ہA�����ۂȂǂƂ����������E�ӔC�m�ɂ��������̏����ȑg�D�ɕ����A���ꂼ��̎�������ѕ���^�c�ɕK�v�ƂȂ鑍���������ׂ��������āA����I�ɕ���^�c���s���d�g�݁B�g�D�S�̂̌o�c�ɂ��đS�E�����l���A�a�@�o�c���������ϊv���Ă�����@�ƂȂ��Ă���B
�@���̎�@�ɂ��A�@���̍�����ÁE���T�[�r�X���i���I�ɒ��邽�߂̕K�v���v�̊m�ہA�A�S���Q���o�c�̎����A�B�o�c�҈ӎ������l�ނ̈琬�A�C���傲�Ƃ̉ۑ�m�ɂ��A�S���ʼn��P�Ɏ��g�ށA�D�e����̊������ʂ𐳂��������A���l�Ƃ��ĉ������邱�Ƃ��\�ƂȂ�A�o�c�ӎ��̏����ƖڕW�Ǘ��̌���A��C�E���[�_�[�̋���E�琬�ɂȂ��Ă���B
�@�u���Z�����a�@�����Ǘ���@�̓����ɂ��E���̕ω��Ƃ��ẮA�@�l���ł̐l�I�𗬂�����������ƂƂ��ɁA�E����l�ЂƂ�Ɍo�c�Q��ӎ����萶���Ă��܂��B�Ⴆ�A�a���t���N���X����DPC�_����f�Õ�V�A�ޗ���Ȃǂ��ӎ������������������悤�ɂȂ�A��t�ȊO�̈�ÐE�����悵�Ď��g�݁A�q�ϓI�Ȏ��т������Ĉ�t���������ޓ������݂��Ă��܂��B�Ⴂ�E���ɏ�����̐ӔC�҂�C���邱�ƂŁA���ԊǗ��E�̈琬�ɂ����ɗL���ƂȂ��Ă��܂��v�i�ɓ��������j�B
�@�J�������P�̎��g�݂�A���Z�����a�@�����Ǘ���@�̓����ɂ����ʂƂ��ẮA�E�������������������A������������E��������邱�ƂŁA�K�v�Ȑl�ނ̗��o��h���A���E�����啝�ɉ��P���Ă���A����23�N�x�ɂ́u�����s���[�N�E���C�t�E�o�����X�F���Ɓv�ɑI�o����Ă���B
�@���ȉ���ɂ��̗p�҂��������Ă���A�Ō�t�̗̍p�ɂ��ẮA���g�݈ȑO�͐l�ޔh����Ђ𗊂炴��Ȃ��ɂ��������A��7�������ȉ���҂ɂȂ�܂ʼn��P�����B����25�N�Ɏ��{�����E�������x�����ł́A���ׂĂ̍��ڂɂ����đ啝�ɉ��P���Ă���A�E�����Ƒ���m�l�ɐE��Ƃ��ďЉ��P�[�X�������Ă���Ƃ����B
�@�u�̗p�ɂ��ẮA�R���i�Јȍ~�͏������������Ƃ��낪����܂����A�l�ޔh���̔�p���팸�������Ƃ�A�l�ނ��m�ۂ��邱�ƂŁh�f��Ȃ��~�}�g�����H�ł��邱�Ƃɂ��A�a�@�o�c�ɂ��悢�e�����o�Ă��܂��v�i�ɓ��������j�B
ICT�����p���A�Ɩ��̕��S�y����}��
�@���̂ق��ɂ��A���@�ł�ICT��ϋɓI�ɓ������A�E���̕��S�y����}���Ă���B
�@ICT�̓����ɂ��āA�����ǒ��̑哇�͎��̂悤�ɐ�������B
�@�u�ʏ�A�d�q�J���e�������p�\�R���̒[���́A�C���^�[�l�b�g�Ɗu�����ꂽ���ɂ���A�����Ƒ�������Ƃ��낪����܂����A���@�ł͓����p�\�R���œd�q�J���e�ƃC���^�[�l�b�g�ɂȂ���d�g�݂������Ă��܂��B�O���[�v�E�F�A��p���āA�E���Ԃ̘A����[�N�t���[�̐\���ȂǁA�����̘J���Ɋւ�邱�Ƃ������p�\�R���łł���̂Ŕ��Ɍ����I�ł��B�܂��A�@�l���̂��ׂĂ̎{�݂��f�[�^�Z���^�[�ƂȂ��邱�Ƃɂ��A����̊���ID�őΉ����邱�Ƃ��\�ƂȂ��Ă��܂��v�B
�@����ɁAAI�����p�����Ɩ����P�̎��g�݂Ƃ��āAAI��f�V�X�e���i�������Ubie������Ёj�����Ă���B
�@�uAI��f�́A�O�����҂ɏǏ�Ȃǂ��^�u���b�g�[���œ��͂��Ă��炤�ƁAAI���œK�Ȏ���������Ŕ��f���Ė�f���s�����̂ɂȂ�܂��B���⍀�ڂ��Œ肳�ꂽ�]���̖�f�����A����ɏڂ���������s���̂ŁA��t�̐f�@���[�������邱�Ƃ��ł��܂��B���@�́A�d�q�J���e�ƃC���^�[�l�b�g�ɓ����p�\�R������Ȃ���d�g�݂������Ă��邽�߁A�^�u���b�g�œ��͂�����f���ʂ��N���E�h����ēd�q�J���e�ɔ��f�����邱�Ƃ��\�ƂȂ��Ă���A�E���̕��S�y���ɂȂ����Ă��܂��v�i�ɓ��������j�B
�@�g�[�^���w���X�P�A�̎����̂��߁A�E���������₷���E����Â���𐄐i���铯�@�̍���̎��g�݂����ڂ����B
�@
�Љ��Ö@�l�Вc������ �����a�@
�������E�@�� �ɓ� ��j��
 �@����̓W�]�Ƃ��ẮA�}���������Â̎������߂Ă������Ƃ͂������A�@�l���O�̍ݑ��ÁA�K��Ō�A��쎖�Ə��Ƃ̘A�g���������A��ÁE���̈�����T�[�r�X���s�����Ƃɂ��A�@�l���O�Ɍf����g�[�^���w���X�P�A���������Ă��������ƍl���Ă��܂��B
�@����̓W�]�Ƃ��ẮA�}���������Â̎������߂Ă������Ƃ͂������A�@�l���O�̍ݑ��ÁA�K��Ō�A��쎖�Ə��Ƃ̘A�g���������A��ÁE���̈�����T�[�r�X���s�����Ƃɂ��A�@�l���O�Ɍf����g�[�^���w���X�P�A���������Ă��������ƍl���Ă��܂��B�@����ŁA����҈�Âɕ�ƁA�f�Â��鎾���������āg�L���A�h�����g�P�A�h�����S�ƂȂ�A��Î҂Ƃ��Ă͏������`�x�[�V�����������肩�˂Ȃ����߁A���x��Â�ۂ��Ȃ���A�n��̈�Ãj�[�Y�ɉ����Ă����B���̂�����̑ǎ��͉ۑ肾�Ǝv���܂��B
�����@�{�݊T�v�@����
| �������^�@�� | �ɓ��@��j | �a�@�J�� | ���a56�N |
| �a���� | 150���i��ʕa��78���A�n���P�A�a��30���A�����n�r���e�[�V�����a��42���j | ||
| �f�É� | ���ȁA�ċz����ȁA�z����ȁA��������ȁA�t�����ȁA�l�H���́A���A�a���ȁA�_�o���ȁA���t���ȁA�O�ȁA���B�O�ȁA���`�O�ȁA������O�ȁA�]�_�o�O�ȁA���NJO�ȁA���O�ȁA�����ȁA��A��ȁA���ː��ȁA���n�r���e�[�V�����ȁA�ɘa�P�A�ȁA���E�}�`�ȁA�畆�� | ||
| �@�l�{�� | �������f�B�J���v���U�a�@�i�ɘa�P�A�Z���^�[�A�t�Z���^�[�A���f�Z���^�[�j�A�������f�B�P�A���ƕ��i�f�Ï��A�Z��^�L���V�l�z�[���A�O���[�v�z�[���A�K��Ō�A�ʏ����n�r���A�ʏ����A������x���A�n���P�A�Z���^�[�j�A���V�l�ی��{�݃C���A�J�[�T | ||
| �Z�� | ��121-0075 �����s�������c��4�|3�|4 | ||
| TEL | 03�|3850�|8711 | FAX | 03�|3858�|9339 |
| URL | https://www.jiseikAI-phcc.jp/tojun_hospital/ | ||
���@���̋L���͌������u�v�`�l�v2025�N7�����Ɍf�ڂ��ꂽ���̂��ꕔ�ύX���Čf�ڂ��Ă��܂��B
�@�@�������u�v�`�l�v�ŐV���̍w�ǂ�����]�̕��͎��̂����ꂩ�̃����N���炨�\���݂��������B


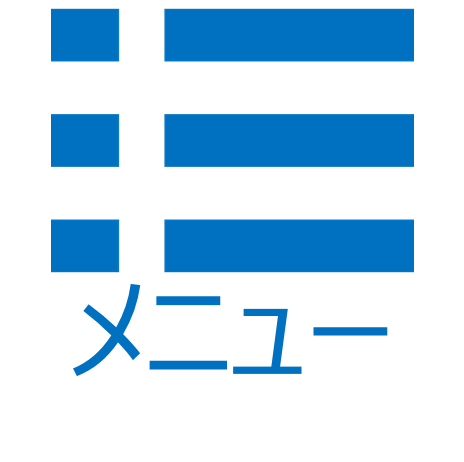

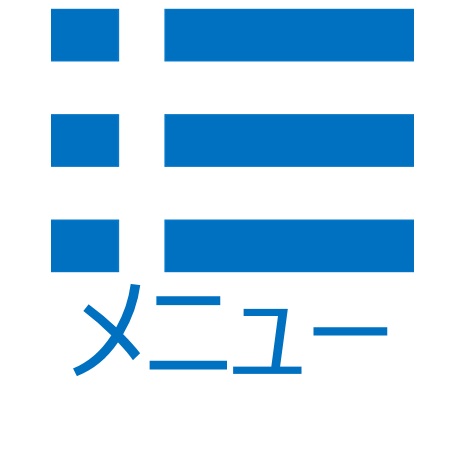
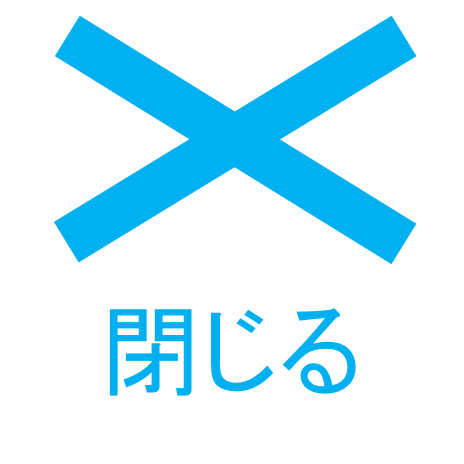
 WAM NET�����p�K�C�h
WAM NET�����p�K�C�h
