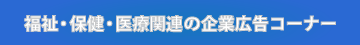|
進行性核上性麻痺進行性核上性麻痺(しんこうせいかくじょうせいまひ)
大脳基底核、脳幹、小脳などの神経細胞が減少して、運動障害等の神経症状がみられ、次第に進行していく疾患です。大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病とともに、パーキンソン病関連疾患に含まれます。 【主症状】 ・発症初期から転倒を繰り返し、立位保持や歩行が困難となります。 ・眼球の運動障害により、特に下方を見ることが困難になります。進行すると眼球は全方向に動かせなくなります。 ・構音障害(話しにくい)、嚥下障害(飲み込みにくい)といった症状が徐々に現れます。 ・認知症を合併します。 ・L-ドパの効果は乏しく、病状が進行します。 【生活上の障害】 ・転倒に関する危険回避行動を取らないことが多く、転倒を繰り返し、骨折や頭部外傷などの重大な事故に至ることもあります。 ・目を離せないため、介護者の負担は重大です。 【予後のリスク】 ・嚥下障害により誤嚥性肺炎が生じやすくなります。 ・食事を経口で摂取できなくなり、人工的水分栄養管理が必要こともあります。 ・パーキンソン病より病状の進行が早く、発症から4〜5年程度で寝たきりになることが多いようです。 ・寝たきりになると、呼吸器や循環器の機能低下により感染、褥瘡などが生じやすくなります。 【気をつけたいこと】 ・転倒の予防が大切です。家の中の転倒しやすい箇所には手すりを設置し、周囲や通路を片付け、不安定なものに体重をかけないよう注意し、トイレなどは余裕をもって行くようにします。 ・外出等の必要に応じ、車いすなどの介護福祉用具を有効に利用しましょう。 ・嚥下障害の状態に気を配り、液体でむせる場合はとろみをつけるなど、適切な食事形態に変更します。食事の際の口への詰め込みなどに対し、声かけや見守りも必要です。
|