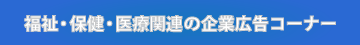|
脳血管障害脳血管障害(のうけっかんしょうがい)
脳梗塞、脳出血、くも膜下出血などによって起こる脳の障害で、障害を受けた脳の部位によって多様な症状あらわす病態です。 【主症状】 ・障害を受けた脳の部位、障害を受けた範囲により異なります。以下は代表的なものです。 ① 運動障害:片麻痺 ② 感覚障害:体性感覚(触覚、痛覚、圧覚、温冷覚、深部覚)、特殊感覚(嗅覚、視覚、味覚、聴覚、平衡感覚など)、内臓感覚 ③ 高次脳機能障害:失語、失認、失行、など ④ 認知機能障害 【生活上の障害】 ・上記の症状によりが生活上注意を払う点が異なりますので、十分症状を把握しその対応を検討しておきます。 【予後のリスク】 ・急性リハビリは非常に重要ですが、回復期、慢性期もリハビリは継続することが必要です。 ・慢性期症状はほぼ固定した後遺症状であり、本人や周囲で関わる者が、日常のリスク管理をする意味でも、その症状を把握しておくことが必要です。 ・意思疎通困難な状態では、新たな病状発生の発見が遅れることがあるので、日常の様子を把握しておくことが必要です。 脳血管障害発症者の多くは、基礎疾患に高血圧症、糖尿病、脂質異常症に罹患していたり、喫煙習慣者であったりしており、多臓器の血管にも何らかの障害が潜んでいる可能性がありますので、その臓器障害の程度により、予後も変わってきます。 また、感染症発症のリスクも高くなります。 【気をつけたいこと】 ・一人ひとり、症状は異なります(全身状態把握)。 ・障害の特徴や程度を正しく把握します(障害程度把握)。 ・個々の特徴に沿って生活環境を整えます(生活環境把握)。 ・周囲からは見えない障害があることを意識し、できないことを責めないようにします(外的サポート)。 ・本人のやるせない気持ちの理解に努めます(個人人生観への理解)。
|