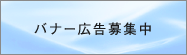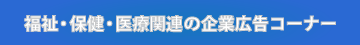|
|
病床機能報告と地域医療構想の概要について病床機能報告と地域医療構想の概要について
1.医療介護総合確保推進法の成立
高齢化の進展に伴う老人慢性疾患の増加により疾病構造が変化し、医療ニーズについては、病気と共存しながら、生活の質(QOL)の維持・向上を図っていく必要性が高まってきています。一方、介護ニーズについても、医療ニーズを併せ持つ重度の要介護者や認知症高齢者が増加するなど、医療および介護の連携の必要性はこれまで以上に高まってきています。また、人口構造が変化していくなかで、医療保険制度および介護保険制度については、給付と負担のバランスを図りつつ、両制度の持続可能性を確保していくことが必要になっています。以上のようなことを背景に、超高齢社会にも耐えうる医療提供体制を構築するため、2014(平成26)年6月、地域における医療および介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律「医療介護総合確保推進法」が成立しました。医療介護総合確保推進法は、持続可能な社会保障制度確立のため、医療法や介護保険法など19の法律が一括で改正され、地域における医療および介護の総合的な確保のための基本的な方針が示されました。 2. 病床機能報告
医療介護総合確保推進法の成立に伴い医療法が改正されたことにより、病床機能報告が医療機関の義務となり、医療機関はその有する病床において担っている医療機能の現状と今後の方向を自主的に選択し、毎年、病棟単位で都道府県に報告することになっています。病院と有床診療所は、病棟単位で医療機能の現状と今後の方向を「高度急性期」、「急性期」、「回復期」、「慢性期」のいずれかから自主的に選択して都道府県に届け出る他、医療機能の報告に加えて、その病棟にどんな設備があるのか、どんな医療スタッフが配置されているのか、どんな医療行為が行われているのか等についても報告します。 3. 地域医療構想策定ガイドライン
厚生労働省は2015(平成27)年3月に「地域医療構想策定ガイドライン」をまとめ、これに沿って、2016(平成28)年度中にすべての都道府県で「地域医療構想」が策定され、2018(平成30)年4月から始まった第7次医療計画の一部として位置づけられました。また、地域医療構想を実現するため、構想区域ごとに「地域医療構想調整会議」が設置され、関係者の協議を通じて、地域の高齢化等の状況に応じた病床の機能分化と連携が進められることになりました。地域医療構想調整会議では、各医療機関が自主的に選択する病床機能報告制度に基づく現状の病床数と地域医療構想における将来人口推計をもとに団塊の世代が75歳以上となる2025(令和7)年の病床の必要量(必要病床数)、さらには医療計画での基準病床数を参考にして、病床の地域偏在、余剰または不足が見込まれる機能を明らかにするとともに、地域の実情を共有し、関係者の協議によって構想区域における課題を解決し、2025(令和7)年に向けた医療提供体制の構築を目指しています。なお、地域医療構想は、二次医療圏を基本に全国で335(2021年10月現在)の「構想区域」を設定し、構想区域ごとに「高度急性期」、「急性期」、「回復期」、「慢性期」の4つの医療機能ごとの病床の必要量を推計します。2025年における医療需要(推計入院患者数)を推計し、それをもとに病床の必要量(必要病床数)を4つの医療機能ごとに推計した上で、地域の医療関係者の協議を通じて病床の機能分化と連携を進め、効率的な医療提供体制を実現する取り組みです。 医療需要の推計方法は「地域医療構想策定ガイドライン」に示されており、4つの機能を医療資源投入量(出来高点数)によって区分しています。医療圏設定の考え方として、二次医療圏は、一般の入院に係る医療を提供することが相当である単位として設定され、地理的条件等の自然的条件、日常生活の需要の充足状況、交通事情等の社会的条件が考慮されています。また、三次医療圏は、都道府県ごとに1つ(北海道のみ6医療圏)計52(2021年10月現在)医療圏とされ、特殊な医療を提供する単位として設定されています。ただし、都道府県の区域が著しく広いことその他特別な事情があるときは、当該都道府県の区域内に二以上の区域を設定し、また、都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に応じ、2以上の都道府県にわたる区域を設定することができることとされています。三次医療圏で提供する特殊な医療の例としては、①臓器移植等の先進的技術を必要とする医療、②高圧酸素療法等特殊な医療機器の使用を必要とする医療、③先天性胆道閉鎖症等発生頻度が低い疾病に関する医療、④広範囲熱傷、指肢切断、急性中毒等の特に専門性の高い救急医療等となっています。
医療機関が報告し、都道府県が2025(令和7)年の必要量を定めることとなる医療機能は、次の4つの区分です
4. 病床機能報告と地域医療構想
病床機能報告制度により報告された情報を公表し、地域医療構想とともに示すことによって、地域の医療機関や住民等が、地域の医療提供体制の現状と将来の姿について共通認識を持つことが可能になります。また、医療機関の自主的な取組および医療機関相互の協議によって、医療機能の分化・連携が進められるようになります。各医療機関における病床の機能分化および連携は、自主的に進めることが前提であり、地域医療構想調整会議は、その進捗状況を共有するとともに、構想区域単位で必要な調整を行います。具体的には、病床機能報告制度における医療機関の報告内容と地域医療構想で推計された必要病床数を比較し、地域において優先的に取り組むべき事項を協議するとともに、消費税増収分を基に各都道府県に設置した地域医療介護総合確保基金の活用等について協議します。 地域医療介護総合確保基金の対象事業には次の5事業があります。①地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業、②居宅等における医療の提供に関する事業、③介護施設等の整備に関する事業(地域密着型サービス等)、④医療従事者の確保に関する事業、⑤介護従事者の確保に関する事業の5事業です。このうち、①地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業については、2018(平成30)年度に対象事業が拡充され、医療機関の事業縮小の際に必要となる費用を計上することが可能となっています。 5.医療計画、市町村介護保険事業計画および都道府県介護保険事業支援計画の整合性の確保
これまでは、医療提供体制は主として都道府県が、介護提供体制は主として市町村が計画を作成してきましたが、今後は、病床の機能の分化および連携の推進による効率的で質の高い医療提供体制の構築並びに在宅医療・介護の充実等の地域包括ケアシステムの構築が一体的に行われるよう、医療計画、市町村介護保険事業計画および都道府県介護保険事業支援計画の整合性を確保することが必要です。それぞれの計画作成に当たっては、患者、介護サービス利用者およびその家族その他の関係者の参画を得ながら計画を作成するプロセスを重視するとともに、計画作成後も、適切な評価項目を設定して、定期的に事後評価が行えるようにすることが求められます。また、都道府県計画は、医療および介護の総合的な確保に関する目標、当該目標の達成に必要な事業に関する事項について定めるものであることから、医療計画および都道府県介護保険事業支援計画の考え方と整合性を図ることが必要です。 6. 切れ目のない医療・介護・予防・住まい・生活支援体制の構築
団塊の世代が全て75歳以上となる2025(令和7)年に向け、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の確保・勤務環境の改善等は急務の課題です。地域医療構想は、高度急性期から急性期、回復期、慢性期まで、将来の医療ニーズの予測を踏まえ、関係者の協議によって地域に必要とされる医療提供体制の整備を進めるものです。一方、地域包括ケアシステムは、要介護の状態になっても可能な限り、住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体制構築を目指すものです。 医療および介護の提供体制については、サービスを利用する国民の視点に立って、ニーズに見合ったサービスが切れ目なく、かつ、効率的に提供されているかどうか、また、高齢化が急速に進む都市部や人口が減少する過疎地等においては、それぞれの地域の高齢化の実状に応じて、安心して暮らせる住まいの確保や自立を支える生活支援、疾病予防・介護予防等との連携が重要です。医療および介護の提供体制を構築し、国民一人一人の自立と尊厳を支えるケアを将来にわたって持続的に実現していくことが、医療および介護の総合的な確保の意義です。地域医療構想と地域包括ケアシステムは、お互いが補完し合うことで、医療と介護の連携を推進し「住み慣れた地域で豊かに老いる」の実現を目指しています。
|