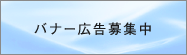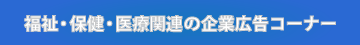|
|
�O���@�\���x�O���@�\���x
1�D�O���@�\�K�C�h���C��
2021�i�ߘa�R�j�N�T���Ɂu�ǎ����K�Ȉ�Â������I�ɒ���̐��̊m�ۂ𐄐i���邽�߂̈�Ö@���̈ꕔ����������@���v�������E���z����܂����B���@�ɂ����āA�n��̈�Ë@�ւ̊O���@�\�̖��m���E�A�g�Ɍ����A�f�[�^�Ɋ�Â��c�_��n��Ői�߂邽�߁A�O���@�\������Ö@�Ɉʒu�Â����A2022�i�ߘa�S�j�N�S�����{�s����܂����B�O���@�\�̎��{��̂́A�u�a���@�\�Ώەa�@���v�ł����ĊO����Â������̂̊Ǘ��҂ł��B�a���@�\�Ώەa�@���Ƃ́A�u�a�@�܂��͐f�Ï��ł����ė×{�a���܂��͈�ʕa����L������́v�ł��B�܂��A���҂���@�����邽�߂̎{�݂�L���Ȃ��f�Ï��i�u�����f�Ï��v�Ƃ����܂��B�j�̊Ǘ��҂��A�O���@�\���s�����Ƃ��ł��܂��B �O���@�\�K�C�h���C���ł́A�@�Ώۈ�Ë@�ւ��s���{���ɑ��āA�O����Â̎��{����邱�Ɓi�O���@�\�Ƃ����܂��B�j�A�A���Y�܂��āA�u�n��̋��c�̏�v�ɂ����āA�O���@�\�̖��m���E�A�g�Ɍ����ĕK�v�ȋ��c���s�����ƁA�B�u��Î������d�_�I�Ɋ��p����O���v��n��Ŋ�I�ɒS����Ë@�ւƂ��āA�u�Љ��f�d�_��Ë@�ցv�m�����邱�ƁA�̂R�̃K�C�h���C����������Ă��܂��B�����ŁA��Î������d�_�I�Ɋ��p����O���Ƃ́A���̇@�`�B�̂����ꂩ�̊O���������܂��B�@��Î������d�_�I�Ɋ��p������@�̑O��̊O���i������ᇎ�p�̑O��̊O�����j�A�A���z���̈�Ë@��E�ݔ���K�v�Ƃ���O���i�O�����w�Ö@�A�O�����ː����Ó��j�A�B����̗̈�ɓ��������@�\��L����O���i�Љ�҂ɑ���O�����j��3�ł��B 2. �O���@�\���x�����̔w�i
���̐��x�����̔w�i�Ƃ��ẮA���҂���Ë@�ւ�I������ɓ�����A�O���@�\�̏�\������ꂸ�A�܂��A���҂ɂ������a�@�u��������Ȃ��ŁA�ꕔ�̈�Ë@�ւɊO�����҂��W�����A���҂̑҂����Ԃ�Ζ���̊O�����S���̉ۑ肪�����Ă��邱�ƁA�܂��A�l�������⏭�q����A�O����Â̍��x�����i�ނȂ��A���������@�\�̋����ƂƂ��ɊO���@�\�̖��m���E�A�g�Ƃ����ۑ肪���邽�߂ł��B�ȏ�̂��Ƃ���A���҂̗���̉~������}�邽�߁A��Î������d�_�I�Ɋ��p����O���̋@�\�ɒ��ڂ��A�Љ��f�d�_��Ë@�ւm�����邱�Ƃɂ��A�a�@�̊O�����҂̑҂����Ԃ̒Z�k��Ζ���̊O�����S�̌y���A�Ђ��Ă͈�t�̓��������v�Ɋ�^���邱�Ƃ�ڎw���Ă��܂��B 3. �Љ��f�d�_��Ë@�ւ̖��m��
�Љ��f�d�_��Ë@�ւ̖��m���ɂ��ẮA��Ë@�ւ��s���{���ɑ��ĊO����Â̎��{��Љ��f�d�_��Ë@�ւƂȂ�ӌ��̗L��������A���Y�܂��āA�u�n��̋��c�̏�v�ɂ����ċ��c���s���A���c����������Ë@�ւ�s���{�������\���邱�ƂƂ��Ă��܂��B�n��̋��c�̏�ɂ����ẮA�Љ��f�d�_��Ë@�ւ̎��܂Ƃ߂ɉ����āA�Љ�E�t�Љ��ƂȂ�n��́u���������@�\��S����Ë@�ցv�ȂǁA�n��̊O���@�\�̖��m���E�A�g�̐��i�̂��߂ɕK�v�Ȏ����ɂ��ĕ��A�f�[�^�Ɋ�Â��c�_���s���K�v������܂��B���̂��߁ANDB�i���Z�v�g���E���茒�f�����f�[�^�x�[�X�j�Ŕc���ł��鍀�ڂ̂����A�n��̊O���@�\�̖��m���E�A�g�̐��i�̂��߂ɕK�v�ȊO���E�ݑ��ÁE�n��A�g�̎��{�ɂ��āA��Ë@�ւ���s���{���ɕ��s�����ƂƂ���Ă��܂��B �n��̋��c�̏�̋c��́A�@�Љ��f�d�_��Ë@�ւ̎��܂Ƃ߂Ɍ��������c�A�A�O���@�\�̖��m���E�A�g�Ɍ��������c�ƂȂ��Ă��܂��B2022�i�ߘa�S�j�N�x�́A�O���@�\���̎{�s���N�x�ł���A�Љ��f�d�_��Ë@�ւ̖��m���Ɏ����鋦�c�𒆐S�ɍs���Ă��܂��B�n��̋��c�̏�̎Q���҂́A��Ö@��̋K��ɑ����āA�S�s���t��̒n��ɂ�����w���o���ҁA��\�����l�������a�@�E�i�L���j�f�Ï��̊Ǘ��ҁA��Õی��ҁA�s�撬�����ł��B�����̎Q���҂ɉ����āA�Љ��f�d�_��Ë@�ւ̎��܂Ƃ߂Ɍ��������c���s���ꍇ�A���̇@�A�A�̈�Ë@�ւ̏o�Ȃ����߁A�ӌ��悷�邱�ƂƂ���Ă��܂��B�@�Љ��f�d�_��Ë@�ւ̈�Î������d�_�I�Ɋ��p����O���Ɋւ����ɊY��������̂́A�O���@�\�ɂ����ďЉ��f�d�_��Ë@�ւƂ��Ă̖�����S���ӌ���L���Ȃ���Ë@�ցA�A�Љ��f�d�_��Ë@�ւ̈�Î������d�_�I�Ɋ��p����O���Ɋւ����ɊY�����Ȃ����̂́A�O���@�\�ɂ����ďЉ��f�d�_��Ë@�ւƂ��Ă̖�����S���ӌ���L�����Ë@�ւƂȂ��Ă��܂��B�܂��A�n��̋��c�̏�ɂ�����O���@�\�̖��m���E�A�g�Ɍ��������c���s���ꍇ�A���c�������ʓI�E�����I�ɐi�߂�ϓ_����A�s���{���́A�c�����ɉ����āA�lj��I�ɎQ�������߂�W�҂�I�肷��ȂǁA�_��ɋ��c�̏���^�c����ƂƂ��ɁA�n��̋��c�̏�ɂ��ẮA��Ö@��A�n���Í\�z������c�����p���邱�Ƃ��\�ł��B 4. �n��̋��c�̏�
�Љ��f�d�_��Ë@�ւ̋��c�́A�O���@�\���琮�����ꂽ�A��Ë@�ւ��Ƃ̏Љ��f�d�_��Ë@�ւƂȂ�ӌ��̗L���A��Î������d�_�I�Ɋ��p����O���Ɋւ����̓K���A�O����Â̎��{�A�Љ�E�t�Љ�̏��܂��ċc�_����܂��B�Љ��f�d�_��Ë@�ւ̎��܂Ƃ߂ɂ����ẮA���Y��Ë@�ւ̈ӌ������ƂȂ�܂��B���̏�ŁA���Y�n��̈�Ò̐��̂�����Ƃ��Ė]�܂����������ɂ��āA�W�ҊԂŏ\���ɋ��c���A���܂Ƃ߂Ɍ��������荇�킹���s�����ƂƂ���܂��B�܂��A��Î������Ãj�[�Y�̏����n��ɂ���ĈقȂ��Ă��邽�߁A��Ë@�ւ̓�����n�搫���l������K�v������A��Î������d�_�I�Ɋ��p����O���Ɋւ������Q�l�ɂ��A���Y��Ë@�ւ̈ӌ��Ɋ�Â��A�n��̋��c�̏�Ŋm�F���邱�Ƃɂ��A�n��̎���܂������̂ƂȂ�܂��B ��̓I�ɂ́A��Î������d�_�I�Ɋ��p����O���Ɋւ�����������Ë@�ւł����āA�Љ��f�d�_��Ë@�ւ̖�����S���ӌ���L����ꍇ�́A���ʂȎ���Ȃ�����A�Љ��f�d�_��Ë@�ւƂȂ邱�Ƃ��z�肳��܂��B�܂��A��Î������d�_�I�Ɋ��p����O���Ɋւ����ƈ�Ë@�ւ̈ӌ������v���Ȃ���Ë@�ւɂ��ẮA���Y�n��̒n�搫�ⓖ�Y��Ë@�ւ̓��������l�����ċ��c���s���܂��B��̓I�ɂ́A�n��̋��c�̏�i�P��ځj�ň�Ë@�ւ̈ӌ��ƈقȂ錋�_�ƂȂ����ꍇ�́A���Y��Ë@�ւɂ����āA�n��̋��c�̏�ł̋c�_�܂��čēx�������s���A���Y��Ë@�ւ̍ēx���������ӌ��܂��A�n��̋��c�̏�i�Q��ځj�ł̋��c���ēx���{���邱�ƂƂ���Ă��܂��B ����ɁA��Î������d�_�I�Ɋ��p����O���Ɋւ����ƈ�Ë@�ւ̈ӌ������v���Ȃ���Ë@�ւ̂����A��Î������d�_�I�Ɋ��p����O���Ɋւ��������Ȃ���Ë@�ւł����āA�Љ��f�d�_��Ë@�ւƂȂ�ӌ���L�����Ë@�ւɂ��ẮA�n��̋��c�̏�ɂ����āA��Î������d�_�I�Ɋ��p����O���Ɋւ����ɉ����āA�Љ�E�t�Љ�������p���ċ��c���s���܂��B��Î������d�_�I�Ɋ��p����O���Ɋւ���������Ë@�ւł����āA�Љ��f�d�_��Ë@�ւƂȂ�ӌ���L���Ȃ���Ë@�ւɂ��ẮA���Y��Ë@�ւ̈ӌ������Ƃ���܂��B�ȏ�̂��Ƃ܂��A���Y�n��̈�Ò̐��̂���������c�̏�A�Љ��f�d�_��Ë@�ւ̎�|���ɂ��Đ������A�Q��ڂ̋��c�Ɍ����ĉ��߂Ĉӌ����m�F���邱�ƂƂ���Ă��܂��B��Ë@�ւ̈ӌ��ƒn��̋��c�̏�ł̌��_���ŏI�I�Ɉ�v�������̂Ɍ���A�Љ��f�d�_��Ë@�ւƂ��A�s���{���ɂ����āA���c���ʂ����܂Ƃ߂Č��\���邱�ƂɂȂ�܂��B 2022�i�ߘa�S�j�N10���ȍ~�́A�Љ��f�d�_��Ë@�ւ̂�����ʕa�� 200���ȏ�̕a�@�ɂ��ẮA�Љ�Ȃ����ғ��̏ꍇ�A�O����f���̒�z���S�̑ΏۂƂȂ邱�ƂƂ���Ă��܂��B���̒�z���S�ɂ́A��z���S�̒�����F�߂��Ȃ��~�}�̊��ҁA���̌���S��Ð��x�̎Ώێғ�����ђ��������߂Ȃ����Ƃ��ł��銳�҂���߂��Ă��܂��B���������߂Ȃ����Ƃ��ł��銳�҂Ƃ́A�Љ��Ȃ��̏��f���҂ł����āA�n��ɑ��ɓ��Y�f�ÉȂ�W�Ԃ���ی���Ë@�ւ��Ȃ����Y�ی���Ë@�ւ��O���f�Â������I�ɒS���Ă���悤�Ȑf�ÉȂ���f���銳�ҁA���茒�N�f���E���f���̌��ʂɂ�萸��������f�̎w���������ғ��ł��B�n��̋��c�̏�ɂ����ẮA�����������O�v�������܂��A�n��ɑ��ɓ��Y�f�ÉȂ�W�Ԃ���ی���Ë@�ւ��Ȃ��ꍇ�ȂǁA���҂��܂��͒n��̢���������@�\��S����Ë@�֣����f���A�K�v�ɉ����ďЉ���ē��Y�Љ��f�d�_��Ë@�ւ���f����Ƃ�����f�̗���ƂȂ�Ȃ��ꍇ�ɂ��āA��Ë@�ւ̓������܂߂Ĕz�����邱�ƂƂ���܂�� �O���@�\�̖��m���E�A�g�Ɍ��������c�ɂ��ẮA�O���@�\�f�[�^������̓��v�������Ŗ��炩�ƂȂ�n��̊O����Ò̐��̌���Ɖۑ�ɂ��āA�Q������W�҂ŔF�������L���邱�ƂƂ��A2022�i�ߘa�S�j�N�x�ȍ~�̊O���@�\����ђn��̋��c�̏�ł̃f�[�^��c�_�̒~�ς܂��āA���L���邱�ƂƂȂ�܂��B��̓I�ȋ��c�����̃|�C���g�◯�ӓ_���ɂ��ẮA���߂Ē���܂��B 5. �Z���̗���
���҂̗���̂���Ȃ�~�����̂��߂ɂ͏Z���̗������K�v�ł��B���c�v���Z�X�̓������̊m�ۂ̊ϓ_������A�s���{���ɂ����Ēn��̋��c�̏�ɒ�o���ꂽ�����̂����A���ҏ����Ë@�ւ̌o�c�Ɋւ�����i��ʓI�ɉ{���\�Ȃ��̂͏����܂��B�j�͔���J�Ƃ��A���̑��̎����A���c���ʂ͏Z���Ɍ��\����܂��B �Љ��f�d�_��Ë@�ւ́A�Љ�҂ւ̊O������{�Ƃ����Ë@�ւł����A���҂ɂ킩��悤�A�L���\�ƂȂ�A��Ë@�\�����x�̍��ڂɒlj����邱�ƂƂ���܂����B����@�\�a�@��n���Îx���a�@�ɂ��Ă��A��Î������d�_�I�Ɋ��p����O���Ɋւ��������A��Ë@�ւ̈ӌ��ƒn��̋��c�̏�ł̌��_����v�����ꍇ�A�Љ��f�d�_��Ë@�ւƂ��čL�����邱�Ƃ��\�ł��B �O���@�\�́A�Љ��f�d�_��Ë@�ւɊւ����Ë@�ւ̈ӌ����܂߁A���N�x�s���{���ɒ�o����܂��B���������Ȃ��ŁA�N�ɂ���āA��Î������d�_�I�Ɋ��p����O���Ɋւ����̍��v�����قȂ邱�Ƃ����蓾�܂��B���̏ꍇ�A���ҕ��S���}�ɕύX����邱�ƂȂǂɂ��A�n��̏Z���ɑ��č����������邱�Ƃ��Ȃ��悤�A��ւ̍��v���ꎞ�I�Ȃ��̂��P��I�Ȃ��̂��Ȃǂ����ɂ߂��J�ɋ��c���邱�ƁA�܂��A�Љ��f�d�_��Ë@�ւ̋��c�̎��܂Ƃ߂ɓ������ẮA�n��̏Z���ւ̎��m�Ȃǂɂ��ď\���ɔz�����邱�ƂƂ���Ă��܂��B
|