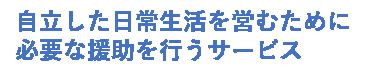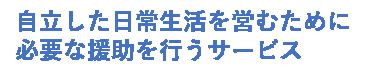居宅において単身等で生活する障害者につき、定期的な巡回訪問または随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題を把握し、必要な情報の提供および助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むために必要な援助を行うサービスです。
対象者
- 障害者支援施設もしくは共同生活援助を行う住居等を利用していた障害者、または居宅において単身であるため、もしくは同居家族等が障害や疾病等のため居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にある障害者。具体的には次のような例が挙げられます。
- 障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障害者等で、理解力や生活力等に不安がある方
- 現に、一人で暮らしており、自立生活援助による支援が必要な方(※1)
- 障害、疾病等の家族と同居しており(障害者同士で結婚している場合を含む)、家族による支援が見込めない(※2)ため、実質的に一人暮らしと同様の状況であり、自立生活援助による支援が必要な方
1の例
(1) 地域移行支援の対象要件に該当する施設に入所していた者や精神科病院に入院していた方等であり、理解力や生活力を補う観点から支援が必要と認められる場合
(2) 人間関係や環境の変化等により、一人暮らしや地域生活を継続することが困難と認められる場合(家族の死亡、入退院の繰り返し 等)
(3) その他、市町村審査会における個別審査を経てその必要性を判断した上で適当と認められる場合
2の例
(1) 同居している家族が、障害のため介護や移動支援が必要である等、障害福祉サービスを利用して生活を営んでいる場合
(2) 同居している家族が、疾病のため入院を繰り返したり、自宅での療養が必要な場合
(3) 同居している家族が、高齢のため寝たきりの状態である等、介護サービスを利用して生活を営んでいる場合
(4) その他、同居している家族の状況等を踏まえ、利用者への支援を行うことが困難であると認められる場合
サービスの内容
- 定期訪問による生活状況のモニタリング、助言
- 随時訪問、随時対応による相談援助
- 近隣住民との関係構築など、インフォーマルを含めた生活環境の整備参考標準利用期間は1年間となっていますが、標準利用期間(1年間)を超えて更にサービスが必要な場合は、原則1回ではなく、市町村審査会の個別審査を要件とした上で、数回の更新が認められます。
利用料
- 18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。その他に、食費などについての実費負担があります。
 | 監修者 | |
| 山本雅章 | 静岡福祉大学福祉心理学科特任教授
調布市社会福祉事業団業務執行理事 |
|