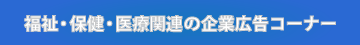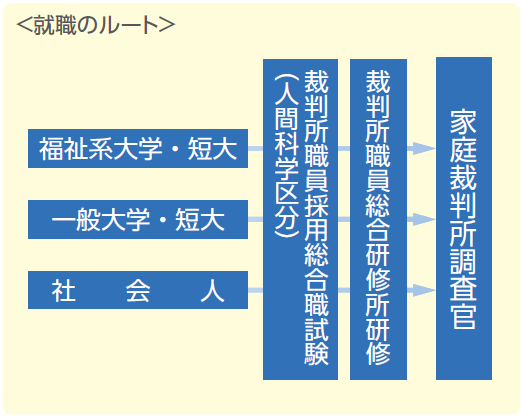�ƒ�ٔ���������
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���i | �������{�N�x��4��1�����݁A21�Έȏ�`30�Ζ����̎ҁA21�Ζ����̑呲����ё呲�����ݎҁA30�Ζ����̑�w�@�C������ё�w�@�C�������ݎ� �����{���Ђ�L���Ȃ��l�A���ƌ������@��38���ɊY������l�͎ł��܂���B |
|
| �������e | ������� | ���e�E�o�蕪��E�o�萔 |
| �ꎟ���� | ��b�\�͎����i�����I�����j | ���ƌ������Ƃ��ĕK�v�Ȋ�b�I�Ȕ\�́i�m�\�y�ђm���j�ɂ��Ă̕M�L���� �m�\����@24�� �m������@6�� |
| ���� | ��厎���i�L�q���j | �ƒ�ٔ�����������ɕK�v�Ȑ��I�m���Ȃǂɂ��Ă̕M�L�����B �@����5�̈悩��o�肳���15��̂����I������2��B �E�S���w�Ɋւ���̈�(3��) �E����w�Ɋւ���̈�(3��) �E�����Ɋւ���̈�(3��) �E�Љ�w�Ɋւ���̈�(2��) �E�@���w�Ɋւ���̈�i���@2��A�Y�@2��j |
| �����_�������i�L�q���j | �g�D�^�c��̉ۑ�𗝉����A���������旧�Ă���\�͂Ȃǂɂ��Ă̕M�L�����@1�� | |
| �l�������T | �l���A�����A�\�͂Ȃǂɂ��Ă̌ʖʐ� | |
| �l�������U | �l���A�����A�\�͂Ȃǂɂ��Ă̏W�c���_�y�ьʖʐ� | |
| ������ | �q�ꎟ�r5������A�q�r6���� | |
| �ꎟ�����y�ѓ����̕M�L���� | �D�y�A���فA���H�A���A�����A�����A�H�c�A�X�A�����A���l�A�������܁A��t�A���ˁA�F�s�{�A�O���A�É��A�b�{�A����A�V���A���É��A�ÁA����A�x�R�A���A���s�A�_�ˁA�L���A�R���A���R�A����A���]�A�����A���m�A���R�A�����A����A�啪�A�F�{�A�������A�{��A�ߔe | |
| �����̐l������ | �D�y�A���A�����A���É��A���A�L���A�����A���� | |
| ��t���� | 3�����{�`4�����{ | |
| �萔�� | ���� | |
�i2024�N�x�`�j
�o�T�F�u�̗p�������v�b�ٔ���
(https://www.courts.go.jp/saiyo/siken/index.html)
�A�E�̃|�C���g
�@���i�͂Ƃ��ɂ���܂��A�ꎟ����b�\�͎����̑����I�����A���L�q���̐�厎���Ɛ����_����������ѐl����������Ȃ�܂��B�������N�A�����������ł��邽�߁A�Љ���w�A�Љ�w�A�S���w�A����w�A�@�w�̂����ꂩ���U���Ď���A�܂��͑�w��Z��ɐi�w����ۂɌ������Ďɔ����邱�Ƃ���ł��B
�@�܂��A�����ł͐l���A�ΐl�I�\�͂Ȃǂɂ��Ă̏W�c���_�ƌʖʐڂ��s���邽�߁A�����납���发��V���A�G���Ȃǂ�ǂނق��A�O���[�v���[�N��[�N�V���b�v�Ȃǂ�ʂ��ăR�~���j�P�[�V�����͂�{���A�W�c���_�ɔ��������A�l�i�`���ɂ��S�����邱�Ƃ��]�܂�܂��B
�@2023�N�x�͐\����694�l�ɑ��A�ŏI���i��75�l�Ƌ�����ɂȂ��Ă��܂��B
�o�T�F�u�ߘa5�N�x���{���� �����E�����i�ƒ�ٔ�����������j�v�b�ٔ���
(https://www.courts.go.jp/saiyo/vc-files/saiyo/2023/saisi/Y-12kekka.pdf)
�֘A�c�́E�g�D
�ō��ٔ�����������