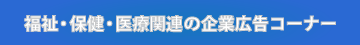���F�S���t
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�ߑO |
���� |
|
�������� |
10�F00�`12�F00�i120���j |
|
�㎋���ҁi1.3�{�j |
10�F00�`12�F40�i160���j |
|
�_�����ҁi1.5�{�j |
10�F00�`13�F00�i180���j |
|
�ߌ� |
���� |
|
�������� |
13�F30�`15�F30�i120���j |
|
�㎋���ҁi1.3�{�j |
14�F00�`16�F40�i160���j |
|
�_�����ҁi1.5�{�j |
14�F00�`17�F00�i180���j |
�@�������̍��ڂƏo�芄����
|
�����̍��� |
�o�芄�� |
|
|
�@���F�S���m�Ƃ��Ă̐E�ӂ̎��o |
��U�� |
|
|
�A�������\�͂Ɛ��U�w�K |
||
|
�B���E��A�g�E�n��A�g |
||
|
�C�S���w�E�Տ��S���w�̑S�̑� |
��R�� |
|
|
�D�S���w�ɂ����錤�� |
��Q�� |
|
|
�E�S���w�Ɋւ������ |
��Q�� |
|
|
�F�m�o�y�єF�m |
��Q�� |
|
|
�G�w�K�y�ь��� |
��Q�� |
|
|
�H����y�ѐl�i |
��Q�� |
|
|
�I�]�E�_�o�̓��� |
��Q�� |
|
|
�J�Љ�y�яW�c�Ɋւ���S���w |
��Q�� |
|
|
�K���B |
��T�� |
|
|
�L��Q�ҁi���j�̐S���w |
��R�� |
|
|
�M�S����Ԃ̊ώ@�y�ь��ʂ̕��� |
��W�� |
|
|
�N�S���Ɋւ���x���i���k�A�����A�w�����̑��̉����j |
��X�� |
|
|
�O���N�E��ÂɊւ���S���w |
��X�� |
|
|
�P�����Ɋւ���S���w |
��X�� |
|
|
�Q����Ɋւ���S���w |
��X�� |
|
|
�R�i�@�E�ƍ߂Ɋւ���S���w |
��T�� |
|
|
�S�Y�ƁE�g�D�Ɋւ���S���w |
��T�� | |
|
㉑�l�̂̍\���Ƌ@�\�y�ю��a |
��S�� | |
|
㉒���_�����Ƃ��̎��� |
��T�� | |
|
㉓���F�S���t�ɌW���鐧�x |
��U�� | |
|
㉔���̑��i�S�̌��N����Ɋւ��鎖�����j |
��Q�� | |
�o�T�F�u���F�S���t�����o���E�u���[�v�����g�v�b��ʍ��c�@�l���{�S�����C�Z���^�[
���i�Ґ�
1,491�l�i2023�N5�����݁j
�o�T�F�u��U����F�S���t�����i�ߘa�T�N�T��14�����{�j���i���\�ɂ��āv�b�����J����
(https://www.sssc.or.jp/touroku/tourokusya.htmlhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33490.html)
���i�擾�̃��[�g
�@���F�S���t�������i�ɂ͈ȉ���8�̃��[�g������܂����A��{�I�ɂ�4�N����w�ŏ���̉Ȗڂ𗚏C��A��w�@���C������A�܂��͎����o����ςނȂǂ��K�{�ƂȂ��Ă��܂��B
�@�Ȃ��A���C���ׂ��Ȗڂ⎩�������ۂɂǂ̋敪�ɊY�����邩�ǂ����͓��{�S�����C�Z���^�[�̃z�[���y�[�W�Łu�̎�����v���Q�Ƃ��Ă��������B
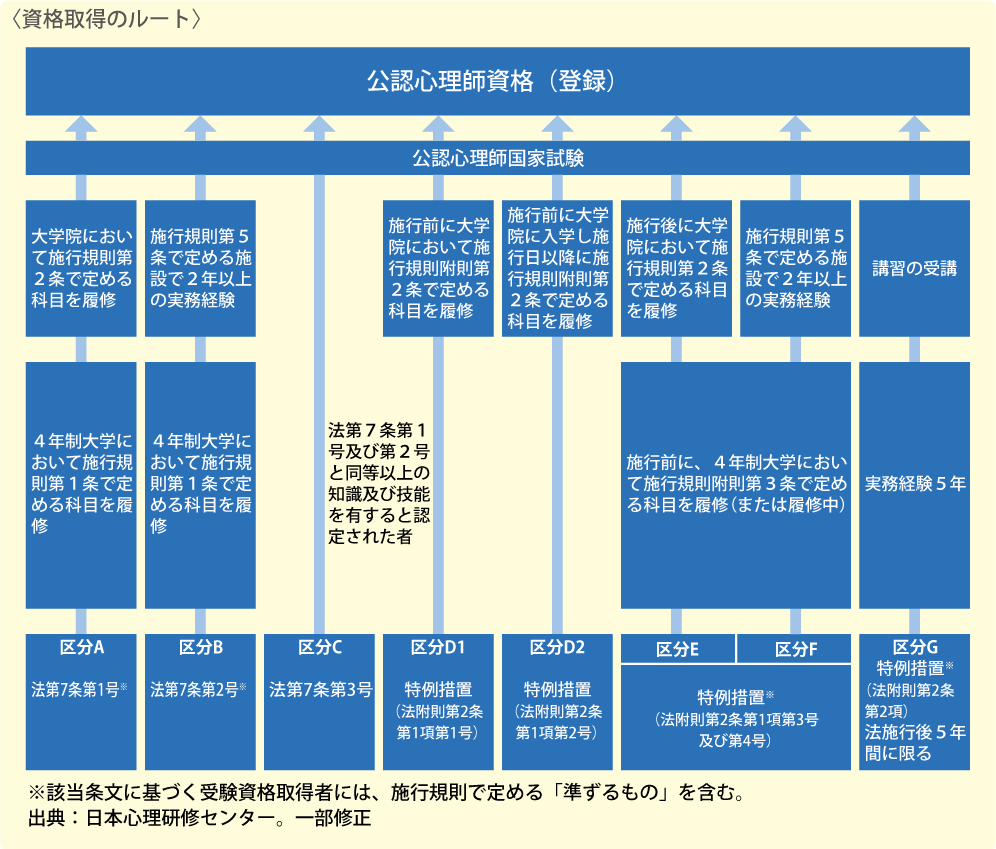
���i�擾�̃|�C���g
�@�Տ��S���m�Ɠ��l�A���i��ɂ͊�{�I�ɂ͑�w�@�܂Ői�݁A���̉Ȗڂ𗚏C���邱�Ƃ����߂��܂��B�܂��A���������{���Ă�����{�S�����C�Z���^�[�̃z�[���y�[�W�Ȃǂŏ��Ă��������B
�֘A�c�́E�g�D�i�S�Ћ��j
��ʍ��c�@�l���{�S�����C�Z���^�[