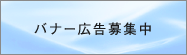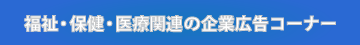認定こども園
|
| 幼稚園 | 保育所 | 認定こども園 | |
| 所管省庁 | 文部科学省 | こども家庭庁 | こども家庭庁 |
| 役割 | 幼児教育 | 保育 | 幼児教育、保育、子育て支援 |
| 対象の子 | 3歳〜就学前 | 保育を必要とする0歳〜就学前 | 0歳〜就学前のすべての子 |
| 1日の時間 | 標準4時間 | 原則8時間 | 4時間8時間ともに可 |
| 長期休業 | あり | なし | 設置者が決める |
| 料金の決定 | 設置者 | 認可/市町村 無認可/施設 | 設置者 |
| 手続き先 | 設置者 | 認可/市町村 無認可/施設 | 設置者 |
| 職員の資格 | 幼稚園教諭 | 保育士 | 0〜2歳児は保育士。 3〜5歳児は両資格の併有が原則(ただし、経過措置あり)。 |
施設数
幼保連携型6,475か所、幼稚園型1,307か所、保育所型1,354か所、地方裁量型84か所、合計9,220か所(2022年4月現在)
出典:「認定こども園に関する状況について(令和4年4月1日現在)」|内閣府
(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0f3ffc2a-7126-4f96-9497-dd3dbfb5438f/123c8b6f/20230929_policies_kokoseido_kodomoen_jouhou_01.pdf)
主な就業職種
保育士、幼稚園教諭
採用について
少子化によって子どもの数は減っているものの、認定こども園も保育所(保育園)と同様、まだまだ子どもに対して施設数が少ないため、とくに待機児童の多い都市部を中心に採用の枠は広いと思われます。
なお、「幼保連携型認定こども園」の職員について幼稚園教諭と保育士試験の両方を有していることを原則としていますが、幼稚園教諭免許状、または保育士資格のいずれかを有していれば保育教諭となることができるとする経過措置が設けられています。この経過措置は2025年3月末までと定められているため、いずれかの資格をもっていれば就職が可能です。
一方、「幼保連携型」以外の認定こども園については、満3歳以上については幼稚園教諭と保育士資格の両免許・資格の併有が望ましいでしょう。また満3歳未満については保育士資格が必要とされています。
関連団体・組織
特定非営利活動法人全国認定こども園協会