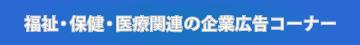生活困窮者自立支援関連情報 |
| 支援調整会議において、以下の点について教えていただきたい。 ① 個人のプラン調整機能と地域づくりの機能を両方持たせて運営するのは難しいのではないか ② 委託先の法人等の担当者の出席をもって、自治体の担当者の参加としてよいか。 ③ 構成員、開催方法や開催頻度はどのように考えればよいか。また、構成員についてはメンバーを固定するのではなく、ケースごとに必要な関係者を招集することとしてよいか。 |
答)
| ○ 支援調整会議の主な目的は、 ① プランの内容が適切なものであるか合議体形式により判断すること ② 参加者が個々のプランに関する支援方針、支援内容、役割分担等について共通認識を醸成し、個々のプランを了承すること ③ プラン終結時において評価を行うこと④ 不足する社会資源について地域の課題として認識し検討することである。したがって、プランを作成する場合には、支援調整会議を開催することが必要となる。また、④については、プランを検討する中で課題が浮かび上がってくるものと考えられることから、支援調整会議の中で検討することとしているが、ここでは課題の整理のみに止め、別途協議の場を設けて対応することも考えられる。また、その場合、新たに協議の場を設けるのではなく、地域資源に関する既存の協議の場を活用することも考えられる。○ 自治体は、プランに法に基づく支援が含まれている場合には、それを支援決定する役割を担うことから、支援調整会議後に無用な手戻りが生じないよう、担当者が出席することが基本と考えている。また、生活保護受給者等就労自立促進事業(ハローワークとの協定による事業)の対象者を定める場合も、自治体が支援調整会議に出席することを必須とする方向で検討している。なお、地域資源の開発を検討するためにも、自治体の参画が重要である。○ 具体的な開催方法については、相談者数や地域資源の状況など地域の実情に応じ会議開催のルールを定めることとなる。例えば、メンバーを固定し定期開催する方式と、ケースごとに開催し必要な関係者のみが集まる方式などが考えられる。自治体の参画を基本としていること等から、固定方式の定期開催をベースとして、事案に応じた随時開催を組み合わせる方式も一案として考えられるところである。 |
| 89 |