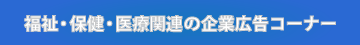サービス取組み事例紹介
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ▲ 施設の外観 |
地域ニーズに応えた福祉サービスを提供
岡山県倉敷市にある社会福祉法人クムレ(理事長:財前民男氏)は、「ともに育ち ともに生きる」という法人理念のもと、地域ニーズに応えた福祉サービスを提供し、地域共生社会の実現に向けて取り組んでいる。
法人の沿革としては、昭和30年に「小ざくら保育園」を開園したことにはじまる。翌年、前身となる社会福祉法人光明会を設立し、地域に根ざした多様な子育て支援事業、発達支援・自立支援事業、就労支援事業を展開しており、平成22年4月に現在の法人名に改称している。
現在は、法人本部のある倉敷市を中心に、岡山市と水島地区の3エリアにおいて、保育所・認定こども園、子育て支援センター、母子生活支援施設、児童家庭支援センター、児童発達支援センター、放課後等デイサービス、障害者入所施設、障害者グループホーム、生活介護、就労継続支援B型事業所、指定特定相談支援事業所など、33事業所を運営している。
なお、法人名は、ラテン語のcum(クム:ともに)とvivere(ウィーウェレ:生きる)を合わせた造語で、地域住民や利用者、職員など多様な人たちと支えあう地域共生社会を目指すという想いが込められている。
重度障害者対応の複合施設を開設
同法人は、令和4年4月に岡山市において、多機能型重度グループホーム「おうちだ」を開設した。同施設は、重度障害者に対応した障害者グループホームをはじめ、ショートステイ、生活介護のほか、児童発達支援、放課後等デイサービス、指定特定相談支援事業所を併設した複合施設となっている。
複合施設を開設した経緯について、理事の安知子氏は次のように説明する。
「令和2年時点の岡山市の施設入所希望者は400人を超え、とくに重度障害者の住まいが不足していました。さらに、医療的ケア児や重症心身障害児を受け入れる事業所も少なく、当法人が倉敷市で運営する児童発達支援センター『倉敷学園』において、定員の半数を受け入れている現状がありました。ショートステイや相談支援事業も十分に整備されておらず、セルフプランにせざるを得ない当事者家族も多く、緊急時の対応も課題となっていました。もともと、当事者家族からグループホームの開設を要望する声が寄せられており、このようなニーズに対応するため、複合施設を開設しました」。
複合施設の開設にあたっては、当事者家族と地域住民、近隣にある大学の学生などが参画するプロジェクトを立ち上げ、地域の意向や要望を確認しながら、地域交流拠点となる施設づくりについて話しあい、開設地の選定においても当事者家族の協力を受けることができたという。
|
|
|
| ▲ 多機能型重度グループホーム「おうちだ」の玄関 | ▲ 1 階のコミュニティスペースは、誰でも気軽に集える場として地域住民に開放している |
|
|
|
| ▲ グループホームの居室とリビング | |
住み慣れた地域でその人らしく暮らすことをサポート
令和4年4月に開設した「おうちだ」は、「どんなに重い障害がある人も、住み慣れた地域でその人らしく暮らす」ことをコンセプトに、児童期から成人期まで切れ目のない福祉サービスを提供している。
建物は2階建てで、各事業所の定員は障害者グループホームが20人(1ユニット10人×2ユニット)、ショートステイが5人、生活介護が15人、児童発達支援・放課後等デイサービスがあわせて5人となっている。施設設計では、1階に地域住民が気軽に集える場としてコミュニティスペースを設け、2階に設置した多目的ホールは、会議やイベント、地域交流活動などに活用するほか、災害時には要配慮者の福祉避難所としての機能を備えた。
障害者グループホームは、「介護サービス包括型」、「外部サービス利用型」、「日中サービス支援型」の3類型があるなか、常時介護を必要とする重度の障害者に対し、24時間対応の支援体制を確保する「日中サービス支援型」として運営している。
グループホームの利用状況について、「おうちだ」管理者の時吉順子氏は次のように説明する。
「利用者の障害支援区分(6段階で数字が大きいほど必要な支援度合いが高い)の平均は5.7で、そのうち医療的ケアが必要な利用者を2人受け入れており、日中は大半の方が、併設する生活介護を利用しています。支援体制では24時間対応のシフトを組むことに苦労しましたが、現在は三交代制と二交代制を組みあわせた勤務体制をとっています。夜間については1ユニット2人ずつの4人を加配した手厚い支援体制としています」。
実践するケアでは、同法人が支援の基本に掲げる「自立・尊厳・ハビリテーション(持っている機能を最大限に活かす)」を軸に、利用者一人ひとりの意思を尊重し、その人らしく生きがいや役割をもって生活してもらうことをサポートしている。
生活介護では、個人の尊厳を保持しつつ、個性や機能、興味・関心に応じた自立した日常生活を送るために運動や個別課題、創作、地域活動などに取り組んでいる。
「生きがいや地域で役割をもつ活動の一つとして、古紙の収集を行うことにより対価を得る取り組みを開始しています。資源の回収場所に運べない地域の高齢者から依頼を受け、スタッフと一緒に自宅まで回収に出かけることもあり、人の役に立つとともに地域に出ていく活動になっています」(時吉氏)。
|
|
|
| ▲ 2 階の多目的ホールは、会議やイベント、親子ひろばの開催などに活用しており、災害時の福祉避難所としての機能を備える | ▲ 社会福祉法人 クムレ おうちだ 管理者 時吉 順子 氏 |
利用児主体の自己選択・意思決定の支援
児童発達支援・放課後等デイサービスでは、主に重症心身障害児を対象とし、利用児主体の自己選択・意思決定の支援とともに、必要に応じて看護師による医療的ケアを行っている。
「対応している医療的ケアとしては、喀痰吸引や人工呼吸器による酸素療法、経管栄養、気管切開など、福祉施設で実施できるものはほぼ対応しています。また、施設内には重度の障害をもつ人に光や音、匂い、触覚など、さまざまな感覚刺激を提供することにより、楽しんだり、リラックス効果のあるスヌーズレンルームを設置しています。意思表出が難しい利用者の好きなことを知る手がかりにもなり、個々の興味・関心に応じた活動に活かすことができています」(安氏)。
また、定員5人のショートステイは、令和6年8月から児童の受け入れも開始しており、母親のレスパイトや親元から離れて生活するなど、さまざま経験を積むことで将来に備えるという目的で利用されているという。
「成人の利用者に比べて手厚い支援が必要になるため、児童を受け入れるショートステイは非常に少ないのですが、当法人の責務だと考えています。その一方で、現在の職員配置では夜間に胃ろうや喀痰吸引などの医療的ケアの対応が必要な人の受け入れが難しく、いずれは対応していかなくてはならない課題だと考えています」(時吉氏)。
|
|
|
| ▲ 入浴支援は、生活介護にとどまらず、児童発達支援、放課後等デイサービスの利用者にも提供 | ▲ 生活介護では、自立した生活を送るため、利用者の個性や機能、興味・関心に応じて運動や創作、地域活動などに取り組んでいる |
|
|
|
| ▲ 施設内にはスヌーズレンルームを設置し、利用者の五感を刺激するとともに、リラッ クスできる環境をつくった | ▲ 児童発達支援・放課後等デイサービスは、主に重症心身障害児を対象とし、自己選択・意思決定の支援や看護師による医療的ケアを行っている |
保育所等訪問支援、公益的事業を実施
そのほかにも、同施設では保育所等訪問支援を実施し、利用児の所属する保育所や学校に保育経験が豊富な担当スタッフが出向き、集団生活に適応していく力が身につくように専門的な支援を行っている。
「保育所等訪問支援は、集団生活の適応が難しいこどもの対応に困っている保育所から相談を受けるケースが多くなっています。初めて育児をする保護者は、こどもの発達に課題があっても気づかないこともありますので、早期に介入するためにも、保護者に対して理解をしてもらえるよう伝えていくことも役割となっています」(時吉氏)。
さらに、公益的な事業活動として、福祉サービスにつながっていない不登校傾向や発達に心配のある児童の居場所を多目的ホールで定期的に開催している。
未就学児の親子を対象にした「ぱんだひろば」では、さまざまな遊びや体験活動を行いながら、専門職に子育てや発達に関する相談ができる場となっている。また、小学生を対象にした「おうちだくらぶ」では、ソーシャルスキルトレーニングを用いて、協調性や社会性などを学び、集団生活に適応していく力を育むことに取り組んでいるという。
複合施設を開設した効果としては、児童期から成人期に至るまで同じ環境で生活のサポートを行うことが可能となり、家族が安心して利用することにつながっている。
「利用者や家族だけでなく、スタッフにとっても複合施設で多職種が連携を図りながら、幅広い支援を経験できることは、支援の質を高めることにつながっています。また、地域交流の活動では、地域住民が野菜等を販売するマルシェや、岡山市が推進する健康づくり体操を定期的に開催し、多くの方に施設に足を運んでいただくことができています。住民同士や利用者との交流が図られるなど、地域共生社会につながっていることを実感しています」(安氏)。
ICTを活用した業務の効率化や災害対策に取り組む
法人全体の取り組みとしては、ICTを積極的に活用して業務の効率化を推進しており、障害者支援では携帯端末を使用した介護記録システム「ケアコラボ」、保育所・認定こども園では登園管理等システムなどを導入している。
「ケアコラボ」は、写真や動画を添付した記録や生活の様子など利用者の情報が時系列に表示され、スタッフや家族が共有できる介護記録システムとなり、業務の共有・連携をスムーズに行うことが可能となったという。
また、災害対策の取り組みでは、平成28年に熊本地震が発生したことをきっかけに、ICTツールの活用により、リアルタイムの情報共有と連携を可能とするBCP(事業継続計画)を作成し、令和3年度に岡山県社会福祉協議会が主催した「福祉施設における災害支援研修会」においてモデル法人として選出されている。
さらに、岡山県DMATに参画し、他機関との連携により災害支援の体制を構築しており、平成30年7月の西日本豪雨災害が発生した際には、倉敷市の法人本部が全国から集まるDMATの拠点としての役割を担った。
地域ニーズに応えた福祉サービスを提供し、地域共生社会の実現を目指す同法人の取り組みが今後も注目される。
社会福祉法人クムレ
理事 安 知子氏
 「おうちだ」は、「どんなに重い障害がある人も、住み慣れた地域でその人らしく暮らす」ことをコンセプトにしていますが、障害の有無に関わらず、ともに生活できるよう地域に働きかけていくことは当法人の役割だと考えています。
「おうちだ」は、「どんなに重い障害がある人も、住み慣れた地域でその人らしく暮らす」ことをコンセプトにしていますが、障害の有無に関わらず、ともに生活できるよう地域に働きかけていくことは当法人の役割だと考えています。また、法人全体では、管理者の育成やマネジメント能力の向上など、人材育成が課題となっています。しかし、福祉側の視点だけでは限界があるため、近年は一般企業の管理者やホテル、テレビ局で働いていた人など、さまざまな分野の方の採用を行っています。他分野のノウハウを学び、これから地域で果たしていく役割を一緒に考えながら、地域共生社会の実現を目指しています。
<< 施設概要 >>
| 理事長 | 財前 民男 | 病院開設 | 令和4年4月 |
| 併設施設 | グループホーム(定員20人)、ショートステイ(定員5人)、生活介護(定員15人)、児童発達支援・放課後等デイサービス(定員5人)、指定特定相談支援、指定障害児相談支援 | ||
| 法人施設 | 認定こども園、保育所、児童発達支援センター、児童発達支援・放課後 等デイサービス、障害者入所施設、障害者グループホーム、生活介護、就 労継続支援B 型事業所、訪問看護ステーション、母子生活支援施設、児 童家庭支援センター、地域子育て支援センター、指定障害児相談支援、居 住支援センター等 | ||
| 住所 | 〒701-0164 岡山県岡山市北区撫川848 | ||
| TEL | 086−238−1802 | FAX | 086−903−1115 |
| URL | https://cumre.or.jp/ | ||
■ この記事は月刊誌「WAM」2024年10月号に掲載されたものを一部変更して掲載しています。
月刊誌「WAM」最新号の購読をご希望の方は次のいずれかのリンクからお申込みください。