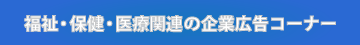サービス取組み事例紹介
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ▲ 施設の外観 |
精神科病院と更生保護施設を運営
東京都町田市にある更生保護法人鶴舞会(理事長:吉川正男氏)は、「安心・安全で良質な医療を提供し、地域医療に貢献する」という理念のもと、精神科病院の飛鳥病院とともに、更生保護事業の更生保護施設を運営している。
法人の沿革としては、昭和34年に財団法人更生保護会愛慈会を設立し、精神科病院の東京愛慈病院と更生保護施設を開設したことにはじまる。昭和40年に病院名を日本精神医療センターに改称し、平成8年に更生保護法により財団法人が廃止となったことに伴い、更生保護法人鶴舞会に改組。平成9年に病院名を飛鳥病院に変更して現在に至っている。
更生保護事業は、犯罪をした人や非行のある少年の改善更生を助けることを目的とした事業で「宿泊型保護事業」、「通所・訪問型保護事業」、「地域連携・助成事業」の3種類がある。更生保護施設は、犯罪や非行をした人を一定期間受け入れ、宿泊場所や食事、自立に必要な支援を提供し、社会復帰をサポートする民間施設となっている。
法人の設立時に、精神科病院と更生保護施設を開設した経緯について、事務部長の佐々木文夫氏は次のように説明する。
「刑務所や少年院の出所者のなかには、精神疾患のために罪を犯したケースがあり、精神科の受診を必要とする人の治療を行うことにより、再犯防止や社会復帰を支援することを目指しています。現在、更生保護施設は、全国102カ所で展開されているなか、更生保護法人が運営している精神科病院は当院が唯一となっています」。
|
|
| ▲ 病院敷地内に設置した更生保護施設の外観 |
地域に根ざした精神科医療を提供
飛鳥病院の病床数は261床で、「利用者のニーズ、時代の変化に適応した医療・看護を目指す」ことを基本方針とし、地域に根ざした精神科医療を提供してきた。
同院の開設地は、東急田園都市線「南町田グランベリーパーク駅」から徒歩10分の好立地にあり、駅直結の複合商業施設や豊かな緑に囲まれた公園とともに、駅周辺は閑静な住宅地が広がる、生活の利便性が高い地域となっている。
実践する医療の特色としては、主に統合失調症やうつ病などの気分障害、認知症の患者を対象とし、急性期から社会復帰まで一貫した治療を行っている。外来診療では、抗精神病薬、抗うつ病薬などの薬剤を用い、患者の症状にあわせ短期間での調整を目指すとともに、医師による診察において患者の心の状態や症状を理解し、協力関係を築きながら問題点を繰り返し整理していくことにより、心の安定や精神症状の改善を図っている。
入院治療では、医師による薬物療法、精神療法に加え、看護師が支える入院生活で規則正しい服薬、睡眠、食事をとってもらい、精神症状の改善を試みている。また、薬剤師が病棟に出向き、服用薬に関する情報を提供するともに、患者の社会生活への適応を目指して積極的なリハビリを導入している。
多職種による精神科リハビリテーションに注力
患者の社会復帰にあたっては、薬物療法に加え、医師や看護師、精神保健福祉士、作業療法士、臨床心理士、薬剤師などの多職種による「精神科リハビリテーション」に力を入れ、デイケア・デイナイトケア、作業療法、訪問看護、心理カウンセリングという4つのリハビリの手段を提供している。
デイケア・デイナイトケアでは、通院中の患者を対象に、生活に必要な基礎的な習慣を身につけ、スポーツや創作、音楽、料理などのさまざまなプログラムを通して生活の質を豊かにするサポートを行っている。作業療法では、患者の希望や治療目的に応じたプログラムを作成し、活動している。
また、訪問看護は令和3年5月より、院内に設置していた訪問看護室から院外の訪問看護ステーションに移行し、退院後の地域での生活を支えている。
「訪問看護ステーションは、看護師7人を配置しており、開設時は当院の患者が9割以上を占めていましたが、地域の医療機関から依頼を受け、現在は利用登録者数が150人を超えています。主に服薬管理や生活の不安などをケアしており、状態に応じて入院につなげています。また、心理カウンセリングでは、臨床心理士が患者の症状の軽減や社会復帰に向けたサポートを行い、症状の理解やリハビリの導入に役立てるため、医師の指示のもと心理検査を実施しています。患者自身が自己理解のために心理検査を利用することもあります」(佐々木事務部長)。
|
|
| ▲ デイケアでは、多様なプログラムを通して生活に必要な基礎的習慣を身につけ、生活の質を豊かにする援助を行う |
病院の全面建て替えを実施
現在、同院は同一敷地内で病院の全面建て替えを実施しており、令和10年7月にフルリニューアルオープンする予定となっている。
「病院の建て替えについては、建物の老朽化が進んでいたこともありますが、当院の外観や病棟は旧来の精神科病院のもつイメージがありました。新病院では落ち着きがありながらも、明るい設計とすることにより、精神科病院のイメージを払拭することを目指しています。さらに、精神科病院としての機能を強化し、立地のよさを活かした『都市型精神科病院』として若年層から高齢層まで幅広い精神疾患に対応していくことを考えています。入院環境については、これまで当院は畳部屋の多床室が多く、コロナ禍のとき感染症対策としてベッド室に切り替えたものの、まだ畳部屋が残っていたため、すべてベッド室として安らぎを感じられる療養環境をつくっています」(佐々木事務部長)。
なお、建て替え計画では、段階的に病棟(本館、新館)の建設、解体を行い、令和7年7月時点でB棟(旧新館)が完成している。最終的には現在の病床数261床から234床にダウンサイジングする予定となっている。
医療機能の強化としては、新たに精神科急性期病棟を開設し、救急搬送の受け入れを開始するとともに、ニーズの高い児童思春期外来を新設して若年層から高齢まで幅広い年齢層の精神疾患に対応していく。また、これまで外来の診療時間は午前のみであったが、診療時間を拡大して外来診療の強化を図るとしている。
先進的な治療の取り組みとして、うつ病では全身麻酔をしたうえで電気刺激を与える治療法「m-ECT」(修正型電気けいれん療法)を実施するほか、これまで治験に取り組んできた経験を活かしながら、新薬による投薬治療にさらに注力していくという。
|
|
|
| ▲ 令和7年7月1日にオープンしたB棟(旧新棟)の個室と多床室 | |
|
|
|
| ▲ 各病棟に設置したデイルームは、明るく安らぎの感じられる空間 | ▲ スタッフステーションは、病棟の中央に設置したことで患者の見守りや対応がしやすくなっている |
再犯防止や社会復帰をサポート
昭和41年に開設した更生保護施設は、建物の老朽化・狭隘化のため、病院敷地内に建て替えを行い、平成24年12月に定員20人の新施設を完成させている。
更生保護施設は、刑務所や少年院の出所者、刑の執行猶予を言い渡された人などのうち、親族や公的機関から援助を受けられない人を対象に、原則として保護観察所から委託されて入所を受け入れている。
受け入れる対象者や近年の傾向について、施設長の根本英男氏(本来は旧字体の英)は次のように説明する。
「当施設は入所定員20人のうち、少年院の退所者枠6人、高齢・障害者枠4人を設け、18歳から65歳以上の幅広い年齢層の対象者を受け入れています。近年は社会的弱者といわれる高齢者、障害者が増え、とくに薬物依存やアルコール依存などの依存症の人が多くなっています。入所者のうち、精神科の治療を必要とする人の割合は、投薬のみの人を含め4割ほどで、飛鳥病院と連携して治療につなげています」。
生活環境では、個室を中心に2人部屋と3人部屋が各1室あり、高齢・障害者用の居室は車いすでも生活できるバリアフリーの個室を設置している。
支援内容としては、宿泊場所と食事の提供とともに、社会生活に適応できるよう生活全般の指導やソーシャルスキルトレーニング(社会生活技能訓練)、就労に向けた伴走支援などを実施している。
薬物依存やアルコール依存がある人に対しては、外部講師を招いた講話や施設職員によるグループミーティングを実施するほか、専門機関のプログラムを通じて依存からの回復に取り組んでいる。また、就労支援ではハローワークへの同行支援を中心に、登録する協力雇用主に受け入れを依頼することが多く、退所後に飛鳥病院の栄養科に就職して厨房での食器洗いを行っているケースもあるという。
「更生保護施設の支援を行ううえでの課題としては、高齢者や障害者の退所後の移行先を探すことが非常に難しくなっています。居住支援法人と連携することが多くなりますが、罪名によっては受け入れ先がないケースも少なくありません。最近は、罪を犯した人の社会復帰に理解のある障害者グループホームに協力してもらい、これまでに4人を受け入れていただいていますが、協力者を増やしていく必要があります」(根本施設長)。
|
|
| ▲ 更生保護施設鶴舞会 施設長 根本 英男 氏(本来は旧字体の英) |
通所・訪問型保護事業として退所後も継続にサポート
退所後の支援では「通所・訪問型保護事業」として、移行先に定期的に訪問し、生活状況を確認して生活の相談などに応じることにより、地域で自立した生活が送れるようサポートしている。さらに、同施設で社会貢献活動や交流会を開催する際には参加を呼びかけ、地域とのつながりをつくることで、孤立や再犯を防止することに取り組んでいる。
飛鳥病院との連携によるメリットとしては、精神科の受診を必要とする入所者が治療を受けられることにとどまらず、病院の厨房で調理した食事を提供したり、経理事務を病院で一括するなど、コストの削減や運営の効率化につながっているという。
現在、医療従事者の確保は全国的な課題となっているが、同院でも専門職の確保は全体的に困難な状況にあるという。
「とくに看護師については非常に厳しい状況があります。ただ、病院が新しくなり、広い駐車場を整備して車で通勤できる環境をつくることで、入職を希望する医療職が増えると考えています。また、採用と同時に働きやすい職場環境づくりも必要となりますが、当院の院長は女性で自身が子育てしながら働いてきた経験から子育て支援を充実させています。産休・育休を取得しやすい職場の風土があり、最近は育休を取得する男性職員も増えています」(佐々木事務部長)。
地域の精神科医療を支えるとともに、社会貢献活動として更生保護事業を行う同法人の今後の取り組みが注目される。
更生保護法人鶴舞会 飛鳥病院
事務部長 佐々木 文夫 氏
 今後の展望としては、建て替え後の新病院をしっかりと運営できる収益体制をつくることが私の役割となります。患者へ良質な医療を提供することはもちろん、職員が働きがいをもち、処遇面でも満足してもらえるためにも、病院経営を安定させていかなくてはならないと考えています。
今後の展望としては、建て替え後の新病院をしっかりと運営できる収益体制をつくることが私の役割となります。患者へ良質な医療を提供することはもちろん、職員が働きがいをもち、処遇面でも満足してもらえるためにも、病院経営を安定させていかなくてはならないと考えています。また、東京都の計画で当院の前に道路が整備されることになっています。これに伴い、新病院の正面は整備される道路に向けて建設しています。この道路が整備されることで、新たに開始する救急搬送の受け入れがしやすくなり、地域住民にとって必要な道路になるため、少しでも早く整備計画が進むよう働きかけていきたいと思います。
<< 施設概要 >>
| 病院開設 | 昭和34年 | ||
| 理事長 | 吉川 正男 | ||
| 病院長 | 田村 由江 | ||
| 病床数 | 261床 | ||
| 診療科 | 精神科、内科 | ||
| 法人施設 | 訪問看護ステーション、更生保護施設 | ||
| 住所 | 〒194−0005 東京都町田市南町田3−8−1 | ||
| TEL | 042−795−2080 | ||
| FAX | 042−799−4573 | ||
| URL | https://www.tsurumaikai-hosp-asuka.com | ||
■ この記事は月刊誌「WAM」2025年8月号に掲載されたものを一部変更して掲載しています。
月刊誌「WAM」最新号の購読をご希望の方は次のいずれかのリンクからお申込みください。