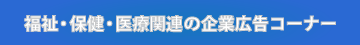令和7年度第4回・診療報酬調査専門組織(入院・外来医療等の調査・評価分科会)(会長:尾形裕也・九州大学名誉教授)が6月19日に開催された。中医協による当分科会は、令和6・7年度と2回にわたって「入院・外来医療等における実態調査」を実施。本年度4回目となる当分科会では、8つの調査項目のうち、「外来医療」についての評価を行った。令和6年度の調査結果をはじめ、2026年度報酬改定に向けた検討材料が盛り込まれ、検討が行われた。
「外来医療」について
全国における外来患者数は、すでにピークを迎え減少局面にあるが、65歳以上の高齢者が占める割合は増加しており、2050年には全体の6割に達すると見込まれる。また要支援・要介護認定者の数も85歳以上で増えると推定され、今後、高齢者に対する適切な医療が提供されることが、外来医療に望まれている。
これからの外来医療は、かかりつけ医としての役割を十二分に機能させるため、全ての病態を把握した包括的な管理を行い、「治す医療」から「治し支える医療」を実現することが重要である。生活機能を保ち、症状を緩和することで、QOLの維持・向上を目指していく医療が求められる。
2025年4月に施行された「かかりつけ医機能が発揮される制度」はそのための指針であり、診療報酬上の新たな評価も加えられている。
これからの外来医療について委員から寄せられた意見は下記の通りである。
○ 外来医療の診療報酬の評価については、かかりつけ医機能報告制度、新たな地域医療構想の方向性におおむね沿った形での整理が重要。
○ いわゆるプライマリケアの継続性、効率性を考える上では、中小病院のかかりつけ医機能を診療報酬上どう評価するかも重要な論点。
○ かかりつけ医機能が発揮される制度が施行され、かかりつけ医機能に関する定義が明らかになった。これらの動向を踏まえると、現行の機能強化加算は新たな考え方に沿っていない。今後制度にフィットした報酬上の評価を検討してはどうか。
○ 特定疾患管療養管理料については、主傷病をピックアップしているが、さらに副傷病名や処方薬なども組み合わせて紹介し、診療実態についてのより詳細な分析を行う必要がある。
○ 生活習慣病管理料においては、計画書のあり方を見直すよい機会になった。また、診療を継続するために予約診療が重要であることが示されたことも大きい。
○ かかりつけ医機能と診療報酬の整理という論点を提示したのは非常に良い。
○ 糖尿病患者の歯科受診だけでなく、オーラルフレイル予防の動機づけとして歯科への定期的受診を促し、口腔機能低下予防対策を行うことも重要になる。
○ フレイルの進行は、病名の重複、ポリファーマシーも含めた服薬の状況等、さまざまなリスクが重なる中で起こる。そこを包括的に診ていく、かかりつけ医の存在は大きい。
○ 総合診療専門医は未だ少ないが、その診療実態がわかる調査の必要性も感じる。
○ 介護との連携、サービス担当者会議への出席やケアマネジャーとの連携の結果が、データとして示されたのは評価できる。
「データ提出加算」について
2022年度診療報酬改定により、「外来データ提出加算」が生活習慣病管理料に新設された。また、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料、在宅がん医療総合診療料における「在宅データ提出加算」、疾患別リハビリテーション料における「リハビリテーションデータ提出加算」も新設されている。
これら加算を届け出ている医療機関数の推移を見ると、いずれも届出数が伸びてはいるものの算定に至っていないところもまだ多く見受けられる。算定できない理由としては、入力のための項目が多く、人員が確保できないこと。また診療所においては、算定のための仕組みが煩雑で理解が難しいという回答が多くみられた。
データ加算提出における課題に関して、現状の評価と進めるべき検討の方向性について以下のような意見が交わされた。
○ データ提出加算については、特に手作業で細部にわたる項目まで入力することが負担となっている。例えば尿酸値のような細かいデータまで必要なのか、検討の余地がある。
○ データ提出加算でないと取れない情報がある一方で、他の方法でも取得できる情報があるのではないか。もっと整理が必要である。
○ 外来データ提出加算の入力項目を見ると、救急受診の状況や入院の状況なども入っている。だが、いきなりこれらのデータを提出するのはハードルが高い。実はこの種のデータは全国医療情報プラットフォームの中からもある程度取得できるので、国でDXを進めていく際に、そういったデータに簡単にアクセスできる環境整備を行い、負担を減らす工夫もあってよいのではないか。
「情報通信機器を用いた診療」について
2022年度の診療報酬改定時、新型コロナウイルス感染症流行の特例措置として、オンライン診療に報酬上の評価がついた。D to P(Doctor to Patient:医師が情報通信機器を用いて患者に診療を行うこと)については以降、算定のための届出件数が増え、初診・再診料の算定回数も増加している。受診者を年齢別に見ると、40歳未満の若年層が多く、60歳以上は少ない。傷病名として最も多いのは、初診料では呼吸器感染症、再診料では精神疾患であった。
また、医学管理における評価として、特定疾患療養管理料、生活習慣病管理料、乳幼児育児栄養指導料、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料、皮膚科特定疾患指導料の順番で多い。在宅管理における評価では、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料、在宅自己注射指導管理料の算定回数が増加傾向になっていた。
オンライン診療に関する調査結果については、以下のような意見が示された。
○ 2024年のデータを見ると、2022年に比べ、精神科領域と皮膚科領域の増加が目立っていると感じる。オンライン診療と対面診療の場合の医療内容がどのように異なっているかなどの比較も行い、実態を検証してはどうか。
○ 皮膚科特定疾患指導料の算定が年々伸びているが、なぜ増えているのか。また、各疾患の算定についても、どのように増えているのか詳細に分析する必要があるのではないか。
○ オンラインでの精神科領域の診療については課題も多く、精神科の専門医の参加も仰ぎ、ワーキンググループでの精査を行ってはどうか。
○ オンライン診療は利便性が評価される一方で、向精神薬の不適切な処方・転売などの社会的問題も起きている。現状初診での処方は認められていないが再診時はOKなので、初診の翌日に再診して睡眠導入剤を処方してもらうケースも問題だ。不適切な対応を行う医療機関を抽出し、ピックアップしていくことが必要。
今検討会の検討スケジュールは、下図の通り。当分科会での議論は、個別事項に関する議論として他の議論とともに取りまとめられ、後日、基本問題小委員会に報告される予定。
3月12日 |
○令和7年度調査の方針
○令和7年度特別調査について(案)
○各作業グループにおける検討状況
|
4月〜 |
○令和7年度調査項目(案)
○令和6年度調査結果(速報)
◆基本問題小委員会に報告
|
|
○個別事項に関する議論
・一般病棟入院基本料
・特定入院料(地域包括医療病棟入院料、特定集中治療室管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料 等)
・療養病棟入院基本料
・外来医療 等
◆基本問題小委員会に報告
|
秋 |
○令和7年度調査結果(速報)
○令和7年度調査結果を踏まえ、個別事項についてさらに議論
・賃上げ/処遇改善等
◆基本問題小委員会に報告
|