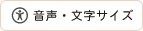

目次


家庭で育てることが難しい乳児を受け入れて養育する
さまざまな事情により家庭で育てることが難しい1歳未満の乳児を受け入れ、授乳や食事、おむつ交換、入浴などの世話をしながら、その子どもが健やかに成長できるようサポートします。
たとえば、心から安心してもらえるよう抱っこしてぬくもりを伝えたり、よく眠れるような環境を整えたり、一緒に遊んだり、体の状態をチェックしたりします。
成長したら親のもとに戻すことを目指す場合は、親の相談にのったり援助したりして、受け入れられるように支援するのも乳児院の役割です。親が子どもを育てることが難しい場合は、里親などの調整も行います。
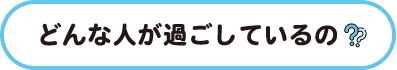

親がいない・育てられないなどの状況にある1歳未満の乳児
出産後に親が亡くなったり、家出したりなどして育てられず、ほかにも子どもを育てられる人がいない1歳未満の乳児が生活しています。また、親がいても、重い病気になったり、育てる力がなかったり、育てるのを拒否、あるいは虐待をするケースもあります。置き去りにされて、親が行方不明という子どももいます。
なお、原則は1歳未満ですが、場合によって小学校入学前まで受け入れることもあります。
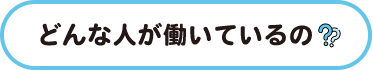

乳児の健康を24時間体制で管理する職員
1歳未満はさまざまな病気にかかりやすくデリケートなため、医師や看護師、保育士により24時間体制で健康管理が行われます。
そのほかにこんな人も!

乳児院で働く保育士の場合
2~3交代制のシフト勤務で、夜勤や宿直もあります。日中は1日8〜9時間勤務する施設が多いようです。
-
- 6:30
-
早番の職員が出勤、子どもたちの着替えなど
 ワンポイント解説子どもたちの起床を確認。看護師による検温など朝の健康チェックの後、着替えやトイレ(おむつ交換)の手伝い
ワンポイント解説子どもたちの起床を確認。看護師による検温など朝の健康チェックの後、着替えやトイレ(おむつ交換)の手伝い
-
- 7:00
-
朝食の介助子どもの月齢に応じてミルクや離乳食などを準備。食後の歯みがきや口の中のケアも
-
- 9:00
-
日勤の職員が出勤。院内での保育 ・散歩
 ワンポイント解説それぞれの子どもの年齢や状態に合わせて遊ぶ
ワンポイント解説それぞれの子どもの年齢や状態に合わせて遊ぶ
今日は晴れていたので、看護師が健康状態をチェックしてから、数人の子どもと近隣を散歩
-
- 11:00
-
子どもたちの昼食の世話
 ワンポイント解説飲み込みがうまくできない様子のAちゃんには、看護師に様子を見てもらった
ワンポイント解説飲み込みがうまくできない様子のAちゃんには、看護師に様子を見てもらった
-
- 12:30
-
子どもの昼寝、職員は昼食を交替でとる
 ワンポイント解説子どもの昼寝を交替で見守る
ワンポイント解説子どもの昼寝を交替で見守る
-
- 14:00
-
午後の院内保育子どもと遊ぶのを他の職員に任せ、担当している子どもの気になる状態について院内で打ち合わせ
-
- 14:30
-
医師が来て、子どもの健康状態をみる一方、家庭支援専門相談員は、親元に戻る子どもの支援計画を作る
-
- 15:00
-
降園の出迎え、おやつを用意保育園から戻る子どもを迎えに行き、その後一緒におやつの時間
-
- 16:30
-
入浴の世話
 ワンポイント解説この時間に出勤する夜勤職員も加え、手厚い体制で入浴を介助
ワンポイント解説この時間に出勤する夜勤職員も加え、手厚い体制で入浴を介助
-
- 18;00
-
子どもたちの夕食夕食後に日勤職員から夜勤職員に申し送りをして、日勤は終業


原則として1歳未満で、親がいなかったり子育てを拒否しているなどの事情を抱える子どもを受け入れ、生活上の世話を行う

生まれたばかりで体の抵抗力が十分についていない子どもの健康を保つ必要があり、医療職など多くの専門職がかかわる必要がある

子どもが成長したときに家に戻る、里親などを手配するなどの調整を行ったり、妊娠中の親への助言や援助、里親を増やすための広報など、幅広い役割を果たす場としての意義が注目されている
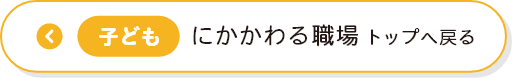

福祉のしごとガイドトップへ戻る











